
『だからオレだめなんだよな…あ、ほらな。またダメって考えてる…』
『オレだって意識高い系なりてーよ!』
『良くないことばっかり頭に浮かんで負のループ…。』
このようにネガティブに捉えてしまう人って多いのではないでしょうか。
特に、面白おかしい自分を演じている人ほど、このような悩みを抱えやすいようです。
そこで今回は、
『マイナス思考をプラス思考に変える5つの方法』
というお話をしたいと思います!
1、フレーミング効果で行動力が身につく【ノーベル経済学賞ダニエル・カーネマン提唱】

表現の仕方によって、他の判断や選択がみちびかれることを、フレーミング効果と言います。
2002年にノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマンさんが提唱した効果です。
たとえば、スポーツジムに通う場面。
入会費いくらですか?
年間3万6500円の負担になります。
ん~迷うな…
フレーミング効果を使って、他の判断や選択をさせてみます。
1日当たり、たった100円で入会できますよ?
うっそ!すっごい安い!入会手続きってどうやるんですか?
表現方法を変えると、行動が変わる、それがフレーミング効果。
100人中95人が企業に失敗するんだよ?
ムリムリ、素直にお墓に帰る…
起業したら100人中5人は成功するんだから、20回挑戦すればいいじゃん。
フレーミング効果を使うと、いろんなことに挑戦できるようになります。
2、課題の分離で悩まなくなる【アドラー心理学】

課題の分離という思考を持つと悩まなくなります。
課題の分離とは、その名のとおり「自分の課題」と「他者の課題」を明確にわけること。そして「他者の課題」には決して踏み込まないことです。
自分の人生において、あなたにできる「自分の課題」は、自分が信じる最善の道を選ぶことだけです。
それについて他者がどのような評価を下すのか、認めてくれるかどうかは「他者の課題」であり、どうしようもできないことです。
たとえば、大学をやめるとき。
大学やめてもいいかな?働きたいんだ。
許しません!認めません!
本当は認めてほしいけど、母さんが認めてくれるかどうかは「母さんの課題」でどうしようもないこと…
- 「他者の課題」はどうすることもできない
- 「自分の課題」は自分で選べる
たとえば、夫が仕事をやめるとき。
今の仕事やめて、転職しようと思うんだ。
収入が下がるなら反対。
月の収入はガクンと下がると思う…
じゃあ反対。それでも仕事を変えるなら離婚する。
課題の分離をしてみます。
- 妻がどう思うかどうかは「妻の課題」
- 転職するかどうかは「夫の課題」
- 妻が離婚するかどうかは「妻の課題」
妻がどう思うかや離婚することに対して、夫は踏み込むべきではない。
夫が転職することに対して、妻は踏み込むべきではない。
他者の課題に踏み込んだとき、人間関係のトラブルに巻き込まれて悩んだり落ち込んだりします。
課題の分離という思考法を身につけると、無駄に悩むことがなくなります。
その結果、ポジティブな自分に変わっていきます。
3、目的論で変わろう【アドラー心理学】

そもそも目的論ってなに?
目的論をわかりやすく説明するために原因論と比較してみます。
たとえば、過去のトラウマが原因で家にひきこもっている人をイメージしてみてください。
原因論でとらえると過去のトラウマが原因で引きこもっています。イジメられたせいで人と触れ合うのが怖い、みたいな。
これに対して目的論でとらえてみます。
ある目的を達成するために引きこもっています。たとえば、親の注目を集めたいという目的。
- 人間の行動には原因がある、と考えるのが原因論
- 人間の行動には目的がある、と考えるのが目的論
もうひとつ例を紹介します。
部下を怒鳴っている上司を原因論で説明します。
上司は、部下がミスをした原因があるから怒鳴っている。
これに対して、目的論で説明します。
上司は、部下に威厳を示す目的があるから怒鳴っている。
というのが原因論と目的論の考え方の違いです。
へーなるほどねー。
…ようするに何が言いたいの?
過去におこった事実は変えることができません。だけど目的なら変えることができます。
過去に起きた事実は変えることができません。イジメとか。ミスとか。
だけど目的なら変えることができます。他の方法で親の注目を集めるとか上司に威厳を感じさせるとか。
自分を変えることができる考え方、それが目的論です。
マイナス思考な自分は何が目的なんだろう?というふうに捉えろってことか。
4、小さな親切をするとネガティブになりにくい【イエール大学の研究データ】

小さな親切をするとネガティブになりにくいという研究データがあります。
小さな親切?
- 歩行者が渡り終えるまで少し待つ
- 両手が塞がってる人のためにドアを開けてあげる
- 立ってるのが辛そうな人に席を譲る
というような他者に対するほんのささいな気遣いのことです。
あのイエール大学の医学部エミール・アンセルさんによる実験です。
成人77名を対象に2週間にわたって調査して、下記の2つを毎日報告してもらいました。
- 日常のストレス度の報告
- 援助行為を行ったかどうかの報告
その結果、親切が多い人はよりポジティブ。さらに、嫌なことがあっても極端に落ち込まない。さらにさらに、明らかにストレスに強い、ということがわかりました。
逆に親切の少ない参加者は、ストレスに弱く、ネガティブな感情から立ち直るスピードが遅かったということがわかった実験です。
小さな親切をするだけでポジティブになれます。
5、ポジティブな人と一緒に過ごす【同調行動】

人は影響を受けやすい生き物です。
なにに影響受けるの?
人や物など、環境に影響を受けます。
たとえば、おいしいレストランで食事をしたいとき。
人が多いほう、賑わってるレストランに入ります。行列ができてる店に入ります。
このように周りの多くの人と同じ行動をとる心理メカニズムを同調行動といいます。
≫ 同調行動とは|集団において周囲の人と同じ行動をとってしまう心理学
類は友を呼ぶとか、朱に交われば赤くなるといった言葉もあります。
- ネガティブな人に同調するとネガティブな思考になる
- ポジティブな人と一緒にいて同調するとポジティブになれる
ポジティブな人と多くの時間を共有すると、同調行動によりポジティブな人になれます。
まとめ
他人を変えるのは難しいです。
他人には他人のストーリーがあるから。
親の愛情をもらうにはテストでいい点をとる必要があった。
いい高校を出ていい大学に入ることが人生の目的となっていった。
社会的な地位がすべて。
「おれはすごいんだぜ!だって部長なんだから!」というストーリーを持ってる上司を、肩書よりも部下を大切にする上司に変えるのは難しいです。
他人を変えるより自分を変えるほうが簡単です。
・表現の違いで、行動を変えることができる
・他者の課題に介入すると悩んで落ち込む
・物事を目的で捉えると変えることができる
・小さな親切でポジティブになれる
・環境が人を変える
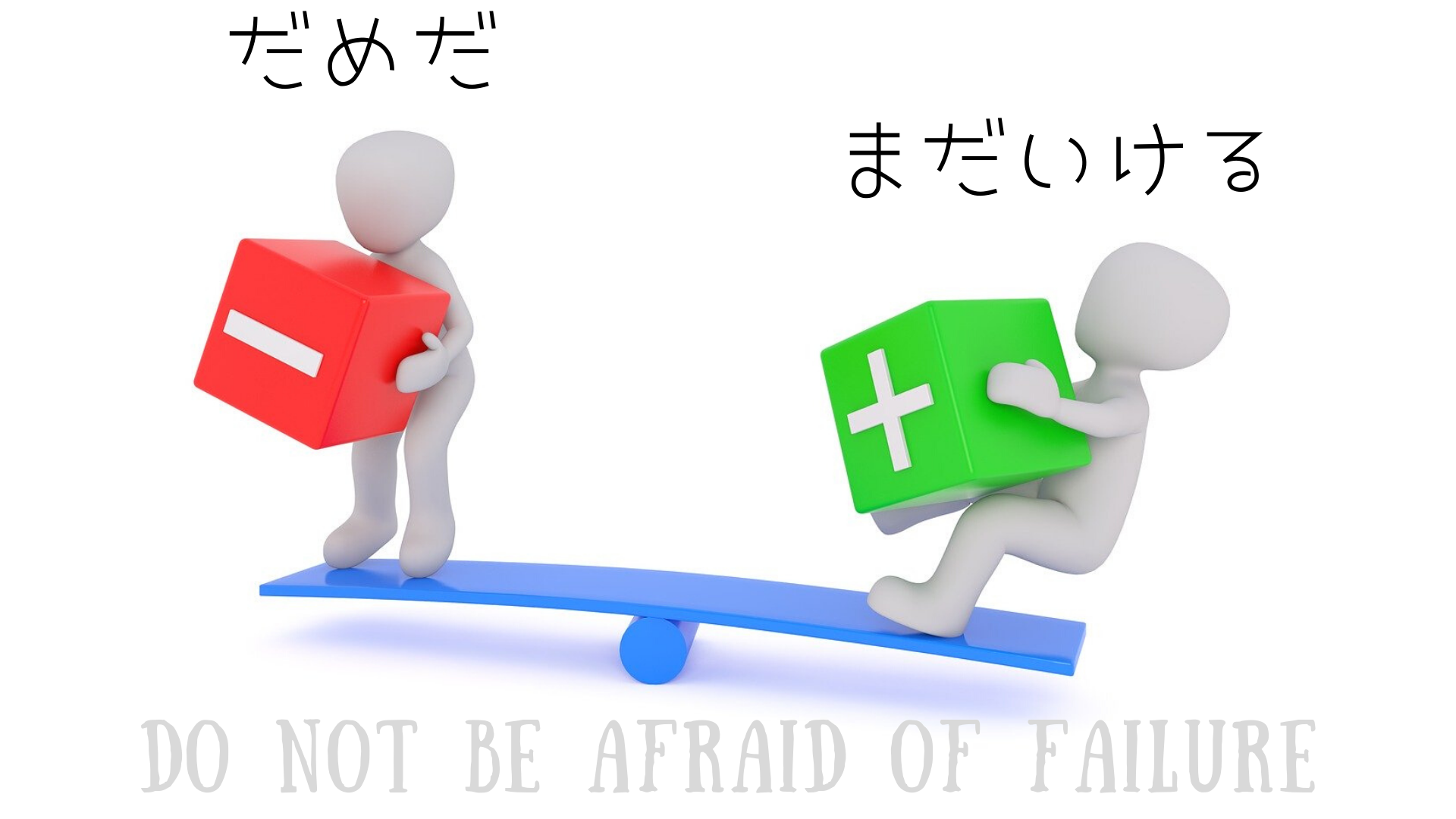
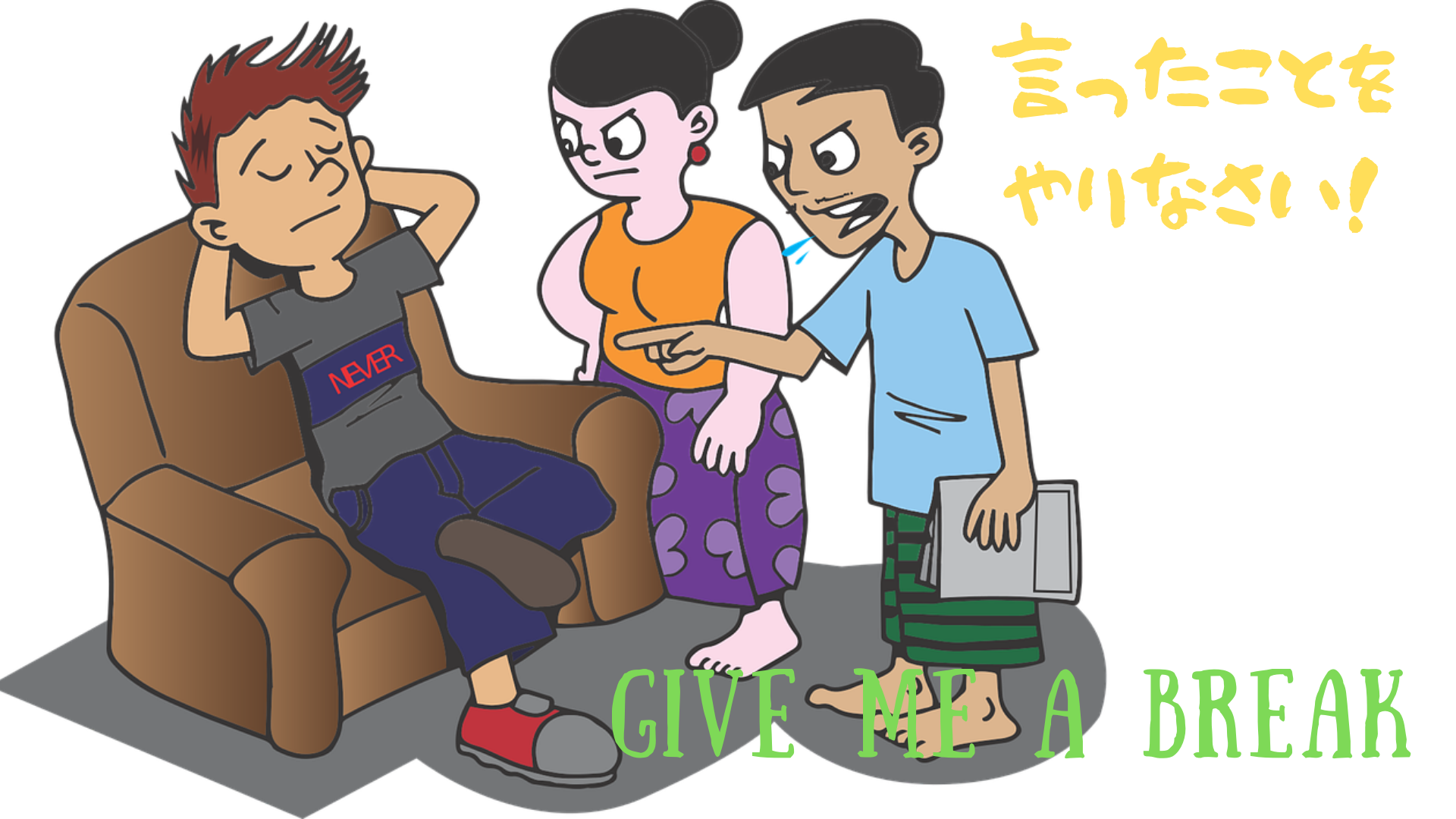

コメントを残す